遺産相続が土地(不動産)しかない場合

比較的容易に分割できる現預金以外に、被相続人が土地や建物といった不動産を持っていたという事例はたくさんあります。このようなケースの場合、相続人同士で解決する方法として、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つが挙げられます。
遺産に土地や建物といった固定資産が含まれる場合や、固定資産のみといった状況は、分割方法がかなり複雑になってきます。実際の相続のケースでは、現預金・有価証券といった現金性資産のものと、土地や建物などの不動産が含まれていますので、遺産の分割方法を知っておいて損はないでしょう。
相続財産が土地や建物といった不動産の遺産分割方法
- 現物分割
-
個々の遺産を、あるがままの形で分け合う、最もシンプルな遺産の分割方法
例)「土地は妻に、預金は長男に」
- 換価分割
-
不動産などを売却することで現金化し、分割しやすい財産に換えることで分割をする方法
| デメリット |
土地を手放さなければならない。また、売却による譲渡税が発生する |
- 代償分割
-
代償金の支払いを行う分割方法
例)「5,000万円の土地を相続人の2人で分け合うために、どちらかの相続人が土地を全て相続し、もうひとりの相続人に2,500万円の支払い(代償)をする」
| デメリット |
代償金を支払う相続人は現金を用意しなければならない |
※代償分割をする場合には、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。
※代償分割した場合の相続税(課税価格)の計算方法
- 代償財産を支払った相続人の課税価格
→ 相続により取得した財産 - 代償財産
- 代償財産を受け取った相続人の課税価格
→ 相続により取得した財産 + 代償財産
- 共有分割
-
個々の遺産を、複数の相続人で共有するという形で相続する分割方法
| デメリット |
土地の管理をめぐって、後でトラブルになることがある。また、その土地を売却・賃貸する場合には、相続人全員の合意が必要になる |
財産目録について
相続にかかる遺産の種類やその価値を把握するためにも、遺産分割協議をするにあたり、被相続人が残した遺産を全て洗い出し、財産目録を作る必要があります。
財産の評価は、分割協議時点での時価で行うのが原則となります。遺産の評価で、その方法の複雑さから問題となるのは不動産評価です。とくに土地評価は、公示価格、基準地価格、路線価、固定資産評価額などで評価に用いられるますがとても複雑です。
■公示価格
| 決定機関 |
国土交通省 |
| 基準日 |
毎年1月1日 |
| 発表日 |
3月下旬頃 |
| 利用方法 |
国土法の指導価格、土地収用の価格 |
| 対象 |
全国の都市計画区域 |
■基準地価格
| 決定機関 |
都道府県 |
| 基準日 |
毎年7月1日 |
| 発表日 |
9月下旬頃 |
| 利用方法 |
公示価格の補完 |
| 対象 |
都市計画区域に限らず全て |
■路線価(相続税評価額)
| 決定機関 |
国税庁 |
| 基準日 |
毎年1月1日 |
| 発表日 |
8月中旬頃 |
| 利用方法 |
相続税・贈与税の算出の基礎 |
| 価格水準 |
80%見当 |
■固定資産税評価額
| 決定機関 |
市町村 |
| 基準日 |
基準年度の前年の1月1日 ※3年に1度、評価が見直しされる |
| 発表日 |
4月初旬 |
| 利用方法 |
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの算出の基礎 |
| 価格水準 |
70%見当 |
※4つを総称して、一物四価といいます。
財産目録について更に詳しく知りたい方はコチラ
遺産分割協議における、土地の価値評価について
相続人全員が納得できれば、相続財産の価値をどう判断するかは自由です。しかし、一般的には一物四価を参考にしたり、不動産鑑定士による評価を用いたりすることで、相続にかかる土地の価値・価格を把握したうえで、不公平のないよう遺産は分配されます。
ただし、土地や建物に関して評価することは素人ではとても困難です。知識と経験のある専門家に相談することをお薦めします。
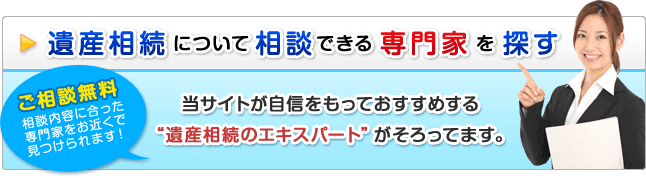
遺産相続の悩みや問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。
遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す