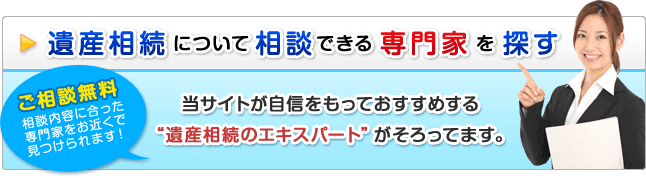生前贈与という言葉をご存知ですか?
生前贈与とは「生きているうち(生前)に財産を譲る(贈与)」ということです。
この「生前贈与」を活用すれば「相続税」を大幅に節約することできます。
親族にできるだけ多くの財産を残したいなら、生前贈与を活用するべきなのです。
この記事では、生前贈与のメリット、その具体的な方法や特例、また生前贈与する際の注意点について、詳しく解説していきます。
「生前贈与」のメリットについて
相続税は2015(平成27)年の制度改正により「基礎控除額」が引き下げられ、「以前は必要がなかった人」まで申告しなければならなくなりました。
さらに、「税率の引き上げ」もおこなわれたため、大幅な増税となったのです。
その一方で、同時に改正された「贈与税」が減税されたことで、「生前贈与」の有効性が高まったのです。
以下では、「生前贈与」の具体的な3つのメリットについて解説します。
メリット1:節税効果が高い
生前贈与の最大のメリットは、「節税効果が高い」という点です。
2015(平成27)年の改正で相続税が増税され、贈与税は減税されたことで、相対的に「生前贈与」を利用する方が多くの資産を残せるようになったのです。
加えて、贈与税に新しく設けられた「特例贈与財産」も節税効果を高める要因になっています。
これにより「20歳以上の直系尊属(子供や孫)」に贈与する場合、「特例税率」が適用され税率が軽減されることになりました。
また、贈与税には教育資金・結婚資金贈与の非課税など「様々な特例」もあるため、有効利用すること大幅な節税が可能になるのです。
メリット2:相続人同士のトラブルを避けることができる
遺産を法定相続人で分割する場合、揉めるケースが多く、裁判にまで発展することも多くなっています。
たとえ遺書があったとしても、その有効性をめぐって争いが起こってしまうのです。
すでに亡くなっている人の意思は確認できないため、簡単には決着がつきません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、生前贈与を利用して資産を渡しておくべきなのです。
仮にトラブルが発生しても、生きていれば話し合いをすることができるので、大ごとになる前に収めることができるでしょう。
メリット3:相続人以外にも資産を渡すことが可能
原則的に、被相続人が亡くなった後、遺産は法定相続人たちによって分割されます。
しかし、生前贈与を活用することで、法定相続人以外にも資産を渡すことが可能になります。
ある特定の資産を「この人に渡したい」という場合など、非常に有効な手段といえるでしょう。
このように、生前贈与は節税効果があるだけでなく、被相続人の意思を最大限反映させることができる制度なのです。
生前贈与の2つの方法
様々なメリットがある「生前贈与」。では、具体的にどのような方法で生前贈与をおこなえばいいのでしょうか。
生前贈与の方法としては、以下の「2つ」があります。
一般的に、生前贈与はこのどちらかを選んでおこなっていきます。
一般贈与の基礎控除を利用する「暦年贈与」
暦年贈与とは、1月1日~12月31日(1年)の間に「1人当たり合計110万円以内」で贈与していく方法です。
これを毎年繰り返せば、たとえどんなに額が大きくなったとしても贈与税はかかりません。
また、贈与を受ける対象者についての制限がないため、親族だけでなく、それ以外の人にも財産を渡すことが可能です。
暦年贈与の具体例
5,000万円の現金を2人(2,500万円ずつ)に相続させるケースを考えてみましょう。
この場合、毎年110万円ずつ暦年贈与すれば、約22年で財産を非課税で渡すことができます。
もし途中で亡くなってしまったとしても、生前贈与していた分だけ「相続財産」が減り、結果として相続税も安く済みます。
当然ですが、5,000万円(2,500万円ずつ)を一度に贈与してしまうと多額の贈与税がかかるためご注意ください。
「連年贈与」には要注意
1年間に110万円以下の贈与であれば、贈与税は一切かかりません。
ただし、ある時期に「10年間にわたって、1,000万円を毎年100万円ずつ贈与する」などと約束した場合は事情が異なります。
この場合、相続税法上では、定期金に関する権利(定期的に分割してお金をもらう権利)を受けたものと考えられます。
実は、この定期金に関する権利は「一括で贈与を受けた」と見なされるため贈与税がかかってきます。これを「連年贈与」といいます。
事前に約束していないとしても、毎年「同月に同額の贈与」がある場合も「連年贈与」と見なされる可能性があります。
連年贈与と見なされないためには、「贈与する月・金額を毎年変える」といった工夫をしなければならないのです。
一度に大きな額の贈与が可能な「相続時精算課税制度」
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合、「2,500万円まで」は非課税とするものです。
2,500万円を超える部分については、「一律に20%」の贈与税を納めることになります。
相続時精算課税制度は節税にならない!?
相続時精算課税制度を利用した場合、2,500万円までは贈与税はかかりません。
ただし、相続が発生した際「相続時精算課税制度で贈与された分」もすべて相続財産に含めた上で、相続税が計算されることになります。
たとえば、全財産7,500万円の内、相続時精算課税制度を利用して「子供1人に2,500万円を贈与」したとします。もちろん、この2,500万円に贈与税が課税されることはありません。
しかし、財産の所有者が亡くなり、相続が発生した場合には残りの5,000万円だけではなく、2,500万円も含めた「7,500万円で相続税を計算」することになるのです。
つまり、相続時精算課税制度は「一時的に相続税を先送りにした」に過ぎないのです。
さらに、「相続時精算課税制度」を選んだ場合、暦年贈与を一切利用できなくなります。そのため、よく考えてからおこなう必要があります。
相続時精算課税制度のメリットはあるの?
一時的に贈与税が非課税になっても、最終的には相続税が課税される「相続時精算課税制度」。そのため、利用しない人が多いのが現状です。
しかし、以下の2つの条件
- 相続財産をすべて含めても基礎控除の範囲内に収まる
- 今すぐ相続人に大きな額を一括で渡したい
を満たしている場合、相続時精算課税制度は有効だと言えるでしょう。
たとえば、全財産3,000万円の内、相続時精算課税制度を利用して子供1人に「2,000万円を一括」で渡したとしましょう。
この場合、贈与税もかからなければ、相続税の基礎控除(=3,000万円+600万×法定相続人の数)の範囲内であるため相続税もかかりません。
うまく使えばメリットもある制度ですが、利用前には必ず専門家に相談してください。
生前贈与の「4つの特例」について
生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度だけでなく、以下の「4つの特例」が設けられています。
- 配偶者控除を利用した居住用不動産贈与の特例
- 住宅取得資金の贈与の特例
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
これらの特例は「暦年贈与や相続時精算課税制度との併用が可能」であるため、うまく活用すれば大きな節税効果が期待できます。
ただし、期間限定のものが多いため、特例を使った贈与をお考えの場合、早い段階で専門家に相談をしてください。
1.配偶者控除を利用した居住用不動産贈与の特例
この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦に限り、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、2,000万円までは非課税で贈与できるという制度です。
また、「贈与税の基礎控除」と一緒に使うことができるので、合計2,110万円の贈与が可能になります。
この特例を受けるためには、以下の条件を満たしていなければなりません。
- 夫婦の婚姻期間が「20年を過ぎた後」に贈与がおこなわれたこと
- 自分が住むための国内の不動産を購入するために贈与がおこなわれたこと など
2.住宅取得等資金の贈与の特例
この「住宅取得等の資金の贈与特例」は、簡単に言うと「子供や孫が家を購入する際、その資金援助であれば700万~1,200万円までは非課税」というものです。
ただし、2015年1月1日から2021年12月31日までの「期間限定の制度」となっています。
また、新しく住宅を取得するための援助資金に限られるため、現在返済中のローンなどはこの対象にはなりません。
下の表は、非課税の限度額を示したものです。表①は消費税8%、表②は消費税10%での限度額となります。
契約をした年によって「非課税の額」が異なるので注意してください。
表①:贈与税非課税の限度額(消費税8%)
| 契約の締結期間 |
「良質な住宅用家屋(※)」の非課税限度額 |
「左記以外の住宅用家屋」の非課税限度額 |
| 2015年1月~12月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
| 2016年1月~2020年3月 |
1,200万円 |
700万円 |
| 2020年4月~2021年3月 |
1,000万円 |
500万円 |
| 2021年4月~12月 |
800万円 |
300万円 |
表②:贈与税非課税の限度額(消費税10%)
| 契約の締結期間 |
「良質な住宅用家屋(※)」の非課税限度額 |
「左記以外の住宅用家屋」の非課税限度額 |
| 2019年4月~2020年3月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
| 2020年4月~2021年3月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
| 2021年4月~12月 |
1,200万円 |
700万円 |
※良質な住宅用家屋とは、「日本住宅性能表示基準」にもとづき、省エネ性や耐震性、バリアフリー性に優れている住宅を指します。
2019年4月以降の契約締結については、表①と②の限度額を比較し、非課税の額が大きいものを採用することになります。
この特例を利用するための条件は以下のようになっています。
- 贈与の対象となるのは子供か孫であること(直系尊属が条件)
- 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
- 贈与を受けた年の「翌年3月15日まで」に住宅を新築や取得していること など
3.教育資金の一括贈与の特例
「祖父母から孫の教育資金を渡す」場合、「教育資金」という名目であれば、1人当たり1,500万円までの贈与を非課税とすることができます。
この特例も「直系尊属」かつ「贈与を受ける側が30歳以下」という条件があります。
また、この「教育資金の贈与」を活用するには、金融機関との「教育資金管理契約」を結び、専用口座を開設しなければなりません。
贈与を受けた人は、必要な時(授業料の支払い等)に口座から引き出し、領収書を銀行に提出する必要があります。
ほとんどの金融機関で扱っているものであるため、ご自身の普段利用されている金融機関に相談してみてください。
教育資金の一括贈与の特例は、「2013年4月1日~2019年3月31日」までの期間限定となっています(期間の内に申し込みを済ませれば適用対象)。
4.結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・出産・子育ての資金であれば、「1人当たり最大1,000万円」までの贈与を非課税とすることができる特例もあります。
ただし、「贈与を受ける側」が2015年4月1日~2019年3月31日までの間、「20歳以上50歳未満」であることが条件になっています(期間内に贈与すれば適用対象)。
- 結婚資金のみの場合:300万円が上限
- 結婚資金・出産資金・子育て資金の場合:1,000万円が上限
贈与の方法としては、金融機関に「結婚・子育て資金」の専用口座を開設し、贈与する金額を預けます。
いまお使いの金融機関にこの特例の取り扱いがあるかご確認ください。
生前贈与のやり方・活用方法がわからない方へ
ここまで、特例も含め「生前贈与のやり方・活用方法」に関して詳しく解説してきました。
生前贈与の方法や特例の使い方がわかったとしても、「自分の資産総額がいくらなのか」「誰にどの程度贈与するのが適切なのか」といった判断は簡単ではなく、非常に悩ましい問題です。
ある特定の人にだけ生前贈与をしたばっかりに、親族の間で争い事が起こってしまったら、元も子もありません。
生前贈与をお考えであれば、まずは税理士・会計事務所、法律事務所といった相続問題のプロにご相談ください。
当サイトが紹介している専門家は、生前贈与だけでなく相続問題をトータルでサポートすることができます。
生前贈与や相続問題に強い専門家はこちらから
生前贈与をおこなう上での注意点
ここまでは生前贈与の活用方法についてご紹介しました。
以下では、生前贈与をする際に「注意すべき4つの点」についてご説明します。
注意を怠れば、多額の贈与税・相続税を支払うことにつながるのです。
注意点1:贈与契約書を必ず作成する
税務調査において「生前贈与」が認められるためには、「誰が見ても贈与がおこなわれた」という証拠を残しておかなければなりません。
そのため、生前贈与をする場合には必ず契約書を作成するようにしてください。
贈与契約書の作成は、特に決まった書式はなく、パソコン・手書きのどちらでも問題はありません。
ただし、契約書には以下のことを必ず記載しておく必要があります。
- 誰が誰に対して贈与するのか
- 何を贈与するのか(現金・不動産など)
- いつ贈与するのか
- どのような条件があるのか
- どのような方法で贈与するのか
贈与契約書に不備があると、「契約そのもの」が無効となり、本来払う必要のない贈与税が発生する恐れがあります。
そのため、生前贈与の額が大きい場合などは必ず専門家に相談した上で「贈与契約書の作成」してください。
注意点2:銀行口座を利用し記録を残す
契約書を作成した上でおこなった生前贈与が、契約書の不備などにより「贈与と認められない」というケースが少なくありません。
そうならないために、「誰が見ても贈与がおこなわれた」という客観的な証拠をできるだけ残しておく必要があります。
現金を贈与する場合、銀行口座を利用することで、「贈与をした日付・金額」が証拠として残すことができます。
名義預金と見なされないよう万全の対策を
また、税務調査では贈与された口座は「誰が管理しているのか」という点も厳しくチェックされます。
その理由は、名義預金(人の名義を借りて預金すること)による脱税を逃さないためです。
生前贈与として、親が子供の口座にお金を振り込んでいても、その口座を親が管理し子供が自由に使えない状態では生前贈与とは認められません。
贈与されたお金は、「贈与を受けた人」が自由に使える状態でなければいけないのです。
生前贈与のお金が振り込まれる「口座の印鑑と通帳」については、「贈与を受けた人自身」が管理してください。
注意点3:早い時期から長期間にわたって贈与をする
生前贈与をおこなう場合、「早い時期から長期間にわたっておこなう」ようにしなければなりません。
なぜなら、相続税法では、亡くなった日(相続開始日)から遡って3年以内に贈与した財産については、「贈与がなかったもの」と見なされるからです。
つまり、亡くなる日の前3年以内におこなった「生前贈与」は認められず、相続税の対象になるということです。
3年以内におこなわれた暦年贈与はどうなるの?
では、毎年110万円以下の贈与をおこなう暦年贈与はどうなるのでしょうか。
残念ながら、亡くなる日の前3年以内におこなわれた「暦年贈与」も相続税が課せられます。
ただし、この対象者になるのは「相続によって財産を取得する者」に限られます。
つまり、法定相続人にはならない人(孫や子供の配偶者など)に暦年贈与をしていれば、相続税が課せられることはありません。
「俺はまだ元気だし生前贈与なんて考える必要はない」
「まだ生きている人に相続の話なんて気が引けてしまう…」
などと、直前まで何の対策もしなければ、相続の段階で大きな損をすることになります。
相続税を節税するためには、生前贈与の計画を立て、長期間にわたって少しずつ贈与をしていくことが何よりも大切なのです。
注意点4:複数の人から贈与を受ける場合、その「合計額」に気をつける
生前贈与は、1人から受けるとは限りません。
たとえば、「父方の祖父」と「母方の祖父」の2人から、1年間の間に「それぞれ110万円ずつの贈与」を受け取ったとしましょう。
1年で110万円であるため、贈与税はかからないように見えます。しかし、贈与は「受け取った額の合計」に課せられるものです。
そのため、上のケースでは「合計220万円の贈与」を1年で受けたことになるので、当然贈与税がかかってくるのです。
生前贈与は「贈与する人・受け取る人」の双方が注意しなければ、想定外の税金が発生することを十分に理解しておいてください。
生前贈与をうまく活用するために
生前贈与は、相続税対策の中で最も効果があるだけでなく、手軽に始めることができます。
しかし、節税の効果を最大限に引き出すには、生前贈与の方法を理解するだけでなく、長期に渡って綿密な計画を立てる必要があります。
こうした手間を怠れば、生前贈与によって「多額の贈与税」を支払うことにもなりかねません。
そのため、「節税のための生前贈与」を考えているのであれば、まずは専門家に相談することをお薦めします。
当サイトが紹介する相続問題の専門家は、無料相談を受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。
親族にできるだけ多くの財産を渡すために、また相続で親族が揉めることがないよう、生前贈与をうまく活用していきましょう。