相続時精算課税制度の対象者が孫まで拡大する可能性があります。
平成25年度の税制改正で、相続時精算課税の対象が孫にまで拡大することは、生前贈与を検討している人にとってどのような意味があるのでしょうか。
簡単に説明すると、今回の改正におけるメリットは、受贈者の人数によって決まる相続時精算課税による非課税枠が増えることです。贈与税の負担なく、次世代に生前贈与によって財産を移転する選択肢が増えることは確かです。
現行の相続時精算課税は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に適用されます。そのため、相続時精算課税の枠は、2,500万円×子の人数。孫に生前贈与を行うためには、まず子に贈与し、子から孫へ贈与するという2段階の形をとるか、孫を養子に取るしかありませんでした。
それが改正により、法定相続人として推定される親だけではなく、20歳以上の孫へ直接贈与をした場合でも贈与税がかからなくなります。子だけではなく孫1人につき2,500万円の枠を獲得することで、人によっては対象となる人数が大幅に増えることになるでしょう。
相続税の増税を見据えた対応をする
贈与税を相続税で精算することが有利とは限りません。平成27年からは相続税の課税最低限が引き下げられ、また最高税率もアップしました。相続税の額はほとんどの人に増額されることになります。
相続税の改正について説明すると、基礎控除額は、現行の
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から
3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
そして税率は以下の表のようになります。
■現行
| 課税標準 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
- |
| 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,700万円 |
■改正後
| 課税標準 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
- |
| 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
| 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
| 6億円超 |
55% |
7,200万円 |
特に相続税増税前の平成26年までの贈与について、相続時精算課税を選択する際には相続税の増税分を勘案した慎重な判断が求められるます。
見落としがちな点としては、孫への贈与について相続時精算課税を適用した場合、原則として相続税が2割加算されることがあります。加算した相続税額を比較対象にしなければ判断を誤ることになります。
平成27年から贈与税の暦年課税の税率構造が変更されることも大きく関係します。暦年課税の項で解説したように、孫への贈与は税率の新たな区分である「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた」場合に該当し、ほかの贈与と比べて贈与税が軽減されています。
個別のケースは税理士に相談を
そもそも、相続問題はいつ発生するかわからないという不確定な要素があります。相続時精算課税が適用できる受贈者が増えることは、有利・不利の判断材料がさらに複雑化することを意味します。
改正前後に関わらず最も重要なことは、事業承継のための贈与、住宅資金のための贈与、教育資金のための贈与など、贈与それ自体にどのような目的があるかをはっきりとさせ、そのための最適な方法を考える視点です。孫に財産を渡したい理由がないのならば、制度適用のためにやみくもに贈与する意味はありません。
相続時精算課税と暦年課税の選択は、目的や財産の内容等、個別のケースに合わせた対応が重要となります。そして、間違いないことは、相続対策は早めに行うことにより、できることの範囲が広がり、効果を高くするということです。早めに税理士などの専門家に相談し、対策することをお薦めします。
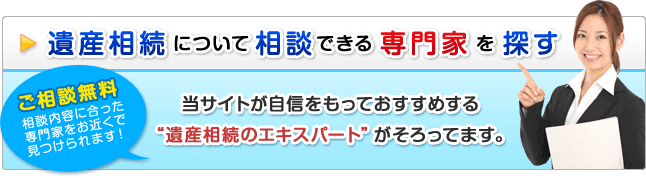
遺産相続の悩みや問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。
遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す